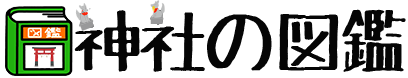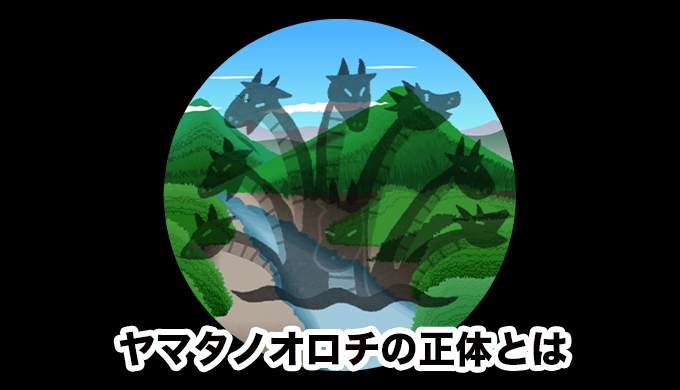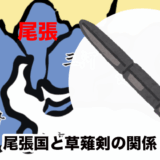ころんくん
ころんくん
今回の記事は、日本神話に残されている「ヤマタノオロチ伝説」の意図について考察を混じり入れながらお伝えしていきたいと思います。
古事記や日本書紀では須佐之男命が出雲国に降り立ち、ヤマタノオロチを退治するお話が残されています。
神話のお話なのでそんな作り話があっても面白いと思いますが
古事記や日本書紀は古代から大切に伝えられてきた日本の歴史を記述した歴史書です。
ただの作り話を1000年以上にわたって伝え重んじてきたと思うと些か疑問を覚えます。
この記事では、ヤマタノオロチ伝説は何を伝えるために記述されたのか?ヤマタノオロチの正体について考えられることをお伝えしていきます。
目次
ヤマタノオロチ伝説とはどんなお話?

まずはヤマタノオロチ伝説についてどんなお話だったのかを確認していきましょう。
話の内容を知っている方は次の章へ飛んでもらっても大丈夫です
神代の時代、「須佐之男命」は姉である「天照大御神」と共に天上の国「高天原」にいました。
須佐之男命はわがままで暴れん坊の性格であった為、傍若無人の限りを尽くして高天原を荒らしていました。
これをなんとかするべく、天照大御神をはじめとした八百万の神々は話し合いを行った結果、
須佐之男命を高天原から追放する結論に至りました。
追放された須佐之男命は罰として汚く伸びきった髭と鋭く尖った手足の爪をすべて剥ぎ取られたそうです。
その後、須佐之男命は出雲国の肥河の川上の鳥髪に降り立ちました。
反省していた須佐之男命はじーっと川を眺めていると上流から箸が流れ下ってきました。
上流に人が住んでいると思った須佐之男命は川を上って行くと老夫婦二人が一人の娘を挟んで泣いていました。
それを見た須佐之男命は老夫婦に理由を尋ねてみました。
するとおじいさんが口を開き
「わしは大山津見の子である「足名椎」と妻の「手名椎」と言い、娘の名は「櫛名田比売」と言います。」
次に須佐之男命はどうして悲しんでいるのかと理由を聞きます。
「私たちの娘はもともと8人おりましたが、毎年この時期になるとヤマタノオロチという怪物がこの辺一帯を襲いにやってきて娘を一人ひとり連れ去ってしまうのです」
須佐之男命は目を大きく開きまるで子供のようにヤマタノオロチに興味を抱きます。
「その大蛇はどんな姿形をしているのかい?」
「その目は酸漿のように真っ赤で、胴体一つに八つの頭と八つの尾があります。
そして、体には日陰蔓や檜と杉の木が生えていて、
その長さは八つの谷、八つの峰に渡っており、その腹を見ると、一面に血が滲んで爛れている恐ろしい姿をしています」
須佐之男命は腕を組み思考を巡らせ、沈黙の後に櫛名田比売の方を一瞥してこう言います。
「私がそのヤマタノオロチを退治して平穏な日々を取り戻してあげよう。
その暁にはそなたのその娘を私の妻として向かい入れたいと思っているのだが・・・」
突然の申し出に老夫婦と娘は鳩が豆鉄砲を食らったかのようにキョトンとした様子でじっと須佐之男命を凝視しました。
足名椎は「恐れ入りますが貴方様はどこのどなたでしょうか?」と恐縮さと不審さが入り混じった面持ちでゆっくり尋ねます。
「私は太陽の神「天照大御神」の弟「須佐之男命」である。
たった今、高天原からこの地に降り立ったところである」
ともっともらしい言いようで言い放ちます。
老夫婦と娘は驚き、一歩二歩後ろに後退り、頭を下げて喜びました。
天上の国では厄介者となっている須佐之男命だが、地上の国では素晴らしい力ある神として言われています。
足名椎と手名椎はヤマタノオロチの脅威から救われる思いと娘を亡くさなくて良くなるかもしれない思いで胸を撫で下ろします。
そして、娘が天照大神の弟である須佐之男命と結ばれるとなると大変に喜ばしいことです。
そうと決まれば話は早いです。
ヤマタノオロチがやってくる時間も迫っているので須佐之男命は早速準備に取り掛かります。
まず、須佐之男命は神の持つ不思議な力「神通力」を使って櫛名田比売を爪形の櫛に化けさせ自分の髪の中へサッと隠し入れました。
ヤマタノオロチは櫛名田比売を求めてやってくるので安全なところに隠す必要がありました。
次に須佐之男命は「足名椎」と「手名椎」に強い酒を用意させました。
ここで使われた酒は八鹽折の酒と呼ばれ、繰り返し醸造したかなり強い酒だったようです。
そして、家の周りに垣根を作り、八つの門を作らせ、さらに門ごとに八つの桟敷を作らせ、そこに八鹽折の酒を酒樽に八つ準備させました。
準備が整うと老夫婦は少し離れた岩陰に避難し、須佐之男命は家の影からヤマタノオロチがやってくるのをジッと待ちます。
しばらくすると、空が次第に漆黒の闇に包まれていくにつれて、凄まじい地響きが音を鳴らしてこちらへ近づいてきます。
ヤマタノオロチです。
八つの頭と尻尾を巧みに動かしながらどんどんこちらへ近づいてきます。
娘を探しているのか八つの頭は辺りを見渡しています。
すると、芳醇な香りを放つ酒に誘われてなのかヤマタノオロチの頭は八つの酒樽めがけてそれぞれ突っ込みます。
巨大な体にも負けない強い酒だったのでヤマタノオロチはあっという間に酔っ払ってしまい眠りについてしまいました。
そこへ須佐之男命が好機と判断し、ヤマタノオロチ目掛けて飛びかかりました。
腰に据えていた「十拳剣」を抜き放ち、酔いがまわって寝込んでいるヤマタノオロチの頭を次々に跳ね飛ばしていきました。
見事、八つの頭を全て跳ね飛ばし、気分が良くなった須佐之男命はついでに八つの尻尾も切り落としはじめました。
1本2本と尻尾を切り落としているとカーンと鈍い音が鳴り響き、十拳剣が欠けてしまいました。
十拳剣は父である伊邪那岐命が使っていた神の剣です。
そんな神霊宿る剣が欠けてしまうことはおかしいと思った須佐之男命はその尻尾を縦に割き中を開いてみました。
すると、中から誰も見たことのない立派な剣が出てきたのです。
須佐之男命は怒らせてしまった天照大御神に謝罪の意味も込めてその剣を献上しました。
(この剣はのちに草薙剣として三種の神器となっていきます。)
見事、ヤマタノオロチを退治した須佐之男命は髪の毛に隠していた櫛名田比売の姿を戻してあげて
約束通り、妻として向かい入れ、須賀宮という宮を建て
「八雲立つ 出雲八重垣 つまごみに 八重垣つくる その八重垣を」
という和歌を歌い二人は静かに暮らしました。
【考察】ヤマタノオロチの正体とは!?何を伝える歴史だったのか?
日本は昔から起こった出来事を後世に伝える手段として童話や童謡といった手法がよく取られています。
これは日本独自の文化でもあり、子供が楽しく理解できるように作られているものがほとんどです。
浦島太郎やかごめかごめと言ったお話や歌がいい例です。
ヤマタノオロチ伝説を見ていただくとお分かりの通り、実際の話ではないことが想像できます。
もし、ヤマタノオロチみたいな生物が存在していたらもっと記述の仕方がより具体的なものとなっていると思います。
では、この伝説は何を伝えるために作られたお話なのでしょうか?
ここからはヤマタノオロチの正体についてその謎を考察を交えながら解き明かしていきたいと思います。
ヤマタノオロチの正体は出雲を流れる巨大な川だった!?

ヤマタノオロチの正体について様々な書籍や記事を読み漁っているとどうやら奥出雲から流れる「斐伊川」という川が八ヤマタノオロチとして比喩されている説が有力のようです。
もともと斐伊川は肥河と呼ばれていた時代があり、出雲大川とも呼ばれるほど出雲国では生活においても重要な河川です。
記録によると古くから度々洪水が起こっており、
たくさんの支流が合流していることから毎年やってくる恐ろしい多頭生物として描かれている模様です。
他にも「足名椎」がヤマタノオロチの特徴を伝えているセリフに
「その長さは八つの谷、八つの峰に渡っており・・・」
とあります。
ここで使われている八という数字は単に数字の八という意味ではなく、
数えきれないほど幾重に重なったという意味合いで幾つにも重なり合った山や谷を体にしていると考えるとしっくりきます。
現在の斐伊川は出雲平野に辿り着くと行き先を西に変え宍道湖へ流れ着いていますが
江戸時代までは西ではなく東へそのまま流れ日本海へ流れていたようです。
つまり、江戸時代までの出雲に住む人々は洪水の被害を平野全体で受けていたことがわかりますね。
ヤマタノオロチは当時の出雲において自然災害の象徴と言えることがわかります。
江戸時代になると治水工事の技術が向上したので川の被害が多い河川は治水工事によって人為的に曲げられています。
斐伊川は寛永12年(1635年)に治水工事を行い宍道湖へ曲げられたようです。
草薙剣はなぜ八岐大蛇から出てきたのか?

ヤマタノオロチの正体と同じくらい不思議な記述が草薙剣の登場場面です。
草薙剣といえば三種の神器のひとつとしても知られ、日本にとって最重要な宝物です。
そんなものが突然、戦利品みたく倒した相手から出てくるのはどういった意味があったのでしょうか?
古代出雲(古墳時代後期)では「たたら製鉄」という伝統的な製法で鉄産業が栄えていました。
たたら製鉄は、土製の炉で砂鉄と木炭を燃焼させて鉄を作ると言ったものです。
 ころんくん
ころんくん
奈良時代に編纂された出雲国風土記によると「この地で生産される鉄は堅く、いろいろな道具をつくるのに最適である」と記されています。
また、たたら製鉄では砂鉄を原料としており、奥出雲では良質な砂鉄が豊富に取れていたようです。
ヤマタノオロチの目は「酸漿のように真っ赤」だと表現されています。
これも製鉄の時にドロドロに溶けた鉄を表していると考えられています。
草薙剣が尻尾から出てきたのはヤマタノオロチの頭を出雲平野にした時、
たたら製鉄が行われていた奥出雲は山奥にあるため尻尾と表現したのかも・・・しれませんね!
伝説に記述があるように当時使われていた剣が欠けてしまうほどの強度だった為、
たたら製鉄で作られた草薙剣は当時日本で一番いい鉄で作られた最高の剣だということがわかります。
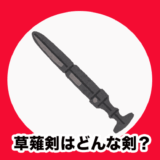 【三種の神器 – 草薙剣】古代より熱田神宮に鎮まる伝説の神剣
【三種の神器 – 草薙剣】古代より熱田神宮に鎮まる伝説の神剣
砂鉄の発掘作業によって奥出雲の山肌は切り崩され溜池や採水路が多く作られました。
そして、砂鉄採取を終えた跡地は棚田として活用され農業として人々の生活を支えていました。
肥河の上流に櫛名田比売がいたのもこれらの背景があったものと推測できます。
櫛名田比売は別名:稲田比売とも呼ばれている田んぼや稲を象徴する女神としても描かれています。
櫛名田比売が須佐之男命に櫛にされてしまったのは須佐之男命と一体になってヤマタノオロチ(肥河)を鎮めていたことが可能性としてあげられます。
古代日本では災害は儀式によってその脅威から身を守っていました。
おそらく、当時の祭司(須佐之男命)と巫女(櫛名田比売)が一体(夫婦)となって行っていたことを暗示しているのかもしれません。
大和と出雲の関係を伝えている?
前述の内容からつながっている部分ではありますが
結末に草薙剣を天照に献上したとあります。
これは古代日本の政略関係を暗示しているのかもしれません。
上記の説を踏まえた上で考えてみるとこのようになります。
高天原(大和)から派遣された須佐之男命は出雲国にやってきました。
争いがあったのかどうかは不明ですがおそらく何らかの形で須佐之男命が出雲国を平定することに成功し、その対価として産業発展していた製鉄産業を手にしました。
それを高天原に献上したということは出雲が大和の支配下に入ったということを暗示しているものと推測できます。
つまり、ヤマタノオロチ伝説では出雲国に関する重要な事柄が詰まったお話ということです。
出雲で作られたものがその後の天皇へ代々継承され、日本建国に大きく影響していたと伝えているのだと思います。
【聖地巡礼】ヤマタノオロチ伝説の地を巡る旅
それでは最後に、八岐大蛇伝説が伝えられている伝承の地をご紹介して行きます。
日本神話の面白いところは実際にその舞台となった場所が日本のどこかに存在するということです。
出雲地方の旅行に行くときの参考にしてみてください!
ヤマタノオロチの住処と伝えられる「天が淵」
天が淵は斐伊川上流、木次町と吉田町境にある場所です。
ヤマタノオロチが住んでいたとされています。
八鹽折の酒を作った場所「布須神社」
布須神社は「足名椎」と「手名椎」が八鹽折の酒を何度も醸した場所として伝えられています。
釜石と呼ばれる釜戸の跡があります。
ヤマタノオロチが酒を飲んだ壺がある!?「八口神社」
八口神社には、大蛇退治の時に「八塩折の酒」を入れた八つの壺のうちの一つがあると伝えられ、「壺神さん」として祀られています。
ヤマタノオロチの頭が埋められている「八本杉」
須佐之男命がヤマタノオロチを退治し終えたおと、切り落とした頭を埋めたとされているのが八本杉の立つ場所です。
長い年月の間、幾度も流失しましたが、その度に捕植され、現在は明治6年(1873年)に植えられたものが残っています。
須佐之男命が櫛名田比売と住む宮跡地「須佐神社」
ヤマタノオロチ退治を終えた須佐之男命は櫛名田比売を妻に向かい入れ新居を作りました。
それが現在の須佐神社のある場所といわれれています。
まとめ:ヤマタノオロチ伝説は出雲国のことを伝える重要なお話
ヤマタノオロチの正体と神話に隠されている様々な内容を紐解いてきました。
この記事でお伝えした内容が本当かどうかはわかりませんが
全く違うということもわかりません。
歴史にはロマンがあるという言葉があるように神話にもロマンがあります。
ヤマタノオロチ伝説が神話として古事記や日本書紀に記述されたのが奈良時代の頃です。
元々、古事記や日本書紀は天皇の正統性を国内外に伝える目的として過去の時代を遡り、日本中に伝わる伝説や口伝等をまとめ一冊の書物にしたものです。
つまり、天皇家にとって都合が良くないといけないということになります。
しかし、日本はどの時代も天皇を中心としているが独裁国家ではありません。
おそらく、神話を作っている時も出雲の末裔の人たちがそばにいた状態だったと思うので
直接的に大和に関係ない出雲の自然災害を盛り込んでいるのだと思います。
本当かどうかわかりませんがね・・・笑
こうしていろんな情報を元に歴史を考えてみると面白いので
ここまで読んでいただけたあなたもいろんな神話の裏側を想像してみるとより日本という国が面白く感じると思います!
それでは今回の記事はここまでです!
神社の図鑑では神社や日本神話に関する様々な事柄を記事にしているので他の記事も読み漁ってみてくれたら嬉しいです!
さようなら!