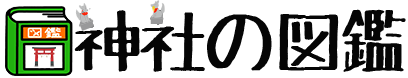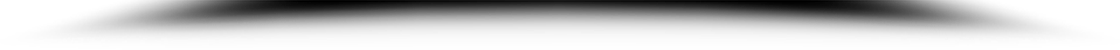〜 由緒 〜
根津神社の創建は日本武尊が東夷征定の途中に須佐之男命の御神徳を仰ぐために千駄木の地に創建されたことが始まりとされる神社です。
現在は「須佐之男命・大山咋神・誉田別命」を御祭神としてお祀りしているが
明治の神仏分離や廃仏毀釈以前は神仏習合が盛んに取り込まれており、「根津三所権現」と呼ばれていました。
根津三所権現は本地垂迹説により、須佐之男命の本地仏に「十一面観音菩薩」、大山咋神(山王大権現)には「薬師如来」、誉田別命(八幡大菩薩)には「阿弥陀如来」となっていました。
江戸時代になると、天台宗の医王山正運寺昌泉院が神宮寺(別当)を務め、根津大権現の社は山王神道の権現社となりました。
文明年間(1469年-1486年)には、江戸城を築城した「太田道灌」により社殿が造られ、
現在の社殿は江戸幕府第5代将軍の徳川綱吉の兄にあたる「甲府藩主徳川綱豊」の屋敷地を献納し、宝永3年(1706)に千駄木の旧社地から遷宮されました。
その後、明治に入り神仏分離・廃仏毀釈によって神仏習合の山王神道などが廃止され
現在の祭祀形態へと変わりました。
境内には見どころも多く、権現社である名残りから残る本殿・幣殿・拝殿が1つにまとめられた権現造を見ることができ、重要文化財に指定されています。
境内社である「乙女稲荷神社」には千本鳥居があったり、
文豪だった「森鴎外」や「夏目漱石」が氏子だったと言われ、腰を下ろした「文豪の石」などがあります。
境内写真
根津神社の評価
パワースポット
(4.0)
御朱印のデザイン
(3.0)
歴史の深さ
(4.0)
境内の雰囲気
(4.0)
アクセスのしやすさ
(4.0)
総合評価
(4.0)
| 所在地 | 東京都文京区根津一丁目28番9号 |
| 創建 | 不明 |
| 本殿の様式 | 権現造 |
| 社格等 | 旧府社 元准勅祭社(東京十社) |
| 御祭神 |
須佐之男命・大山咋神・誉田別命 相殿神:大国主命・菅原道真公 |
| 御朱印 | 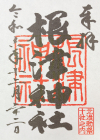 |
| 神事 / 祭事 | 例祭:9月21日 |
| アクセス |
車の場合 公共交通機関の場合 東京メトロ千代田線「根津駅」・「千駄木駅」より徒歩5分 東京メトロ南北線「東大前駅」より徒歩5分 都営三田線「白山駅」より徒歩10分 |
| 駐車場 | 境内参拝者専用駐車場あり 3台 |
| 参拝時間 | 24時間参拝可能 |
| 社務所/授与所 | 9:00 ~ 17:00 |
| 電話番号 | 03‐3822-0753 |
| 公式HP | https://nedujinja.or.jp/ |
| 神紋 |  |
境内図