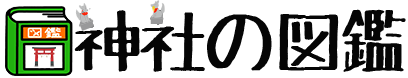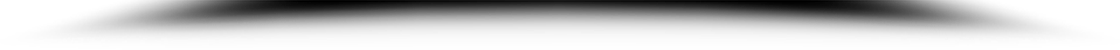〜 由緒 〜
愛宕神社は、東京都港区の愛宕山山頂に鎮座する「火産霊命」をお祀りする神社です。
愛宕山は天然の山として東京23区の中で一番高いとされる標高25.7mを誇っています。
江戸を護る信仰の対象となっており、慶長8年(1603年)に徳川家康の命により、
滋賀県甲賀市信楽町にある「新宮神社」の境外摂社愛宕神社を勧請し、
防火の神(愛宕権現)を祀り創建されたとされたと伝わります。
また、徳川家康の希望によって「勝軍地蔵菩薩」が合わせてお祀りされることになり
防火の役割だけではなく、「天下取りの神」「勝利の神」としての一面もあることで知られていました。
その後、明治の廃仏毀釈によって勝軍地蔵菩薩像が祀られていた「別当寺 円福寺」が廃寺となり
近くの真福寺へ移されたが大正12年(1923年)に発生した関東大震災で焼失してしまいました。
1934年に弘法大師1100年御遠忌記念として銅製で復元され、
現在は、1997年に建設された真福寺・愛宕東洋ビル一階外側に祀られています。
愛宕山は急勾配の斜面を要する山でもあり、境内に上がるためには壁のような石段86段を登る必要があります。
この階段を別名「出世の石段」と呼ばれており、ある逸話が残されています。
かつて、三代将軍「徳川家光」が愛宕山の麓から山頂に咲く梅を取って参れと家臣に申しつけました。
しかし、急勾配の石段を馬で上がることは難しく、家臣たちは躊躇していました。
そんな中、四国丸亀藩士の曲垣(曲木)平九郎が馬に乗って見事に駆け上がり梅を家光に献上しました。
家光はその馬術を称賛し「日本一の馬術名人」と讃え、平九郎の名は一日にして全国にとどろいたと伝えられました。
名も無い藩士が愛宕神社の石段によって見事に出世を果たしたことからこのように呼ばれるようになったとか・・・
境内写真
| 所在地 | 東京都港区愛宕一丁目5番3号 |
| 創建 | 慶長8年(1603年) |
| 本殿の様式 | 神明造 |
| 社格等 | 旧村社 |
| 御祭神 | 火産霊命 |
| 御朱印 | 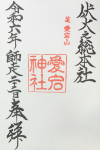 |
| 神事 / 祭事 | 出世の石段祭(隔年):9月22日~24日 大祭式:9月24日 11時 |
| アクセス |
車の場合 首都高速都心環状線「霞ヶ浦IC」から1.3km 約5分 公共交通機関の場合
|
| 駐車場 | 参拝者専用無料駐車場6台(9時から16時まで) |
| 参拝時間 | 24時間参拝可能 |
| 社務所/授与所 | 9:00 ~ 17:00 |
| 電話番号 | 03-3431-0327 |
| 公式HP | https://www.atago-jinja.com/ |
| 神紋 |   |