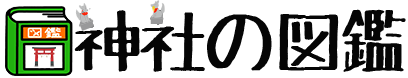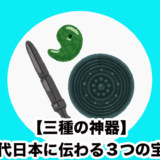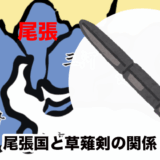ころんくん
ころんくん
今回の記事は、三種の神器の一つ「八尺瓊勾玉」をご紹介していきたいと思います。
八尺瓊勾玉は三種の神器である「鏡」「剣」「勾玉」のうち、勾玉を担う日本の宝物です。
古代日本の時代から天皇家によって代々継承され、
三種の神器のうち唯一、天皇が宮中にて祀りあげているものと言われています。
八尺瓊勾玉は三種の神器であることはご存知の通りなのですが
どうして三種の神器に「勾玉」が入っているのでしょうか?
鏡は天照大御神そのものを象徴し、剣は権力や支配または勇気を象徴するものと考えられています。
では、勾玉は何を意図して三種の神器に組み込まれたのでしょうか?
この記事では、八尺瓊勾玉についてお伝えしていくとともに
勾玉がどうして三種の神器として選ばれたのか?についてもお伝えしているので
ぜひ最後まで記事を読み進めていってください。
目次
八尺瓊勾玉とは

八尺瓊勾玉は三種の神器のひとつとして古代日本から天皇家によって代々継承されてきた日本の宝物です。
日本の歴史に初めて登場したのは日本神話の天岩戸隠れ伝説です。
天照大御神が岩戸に隠れてしまった際、八百万の神々が天岩戸から天照大御神を引き摺り出す作戦を考え、実行しました。
その時に玉祖命が八尺瓊勾玉を作り、八咫鏡と共に真榊の木に掛けたのが初登場のお話です。
その後、天孫降臨の神話で天照大神から瓊瓊杵尊へ三種の神器として授かり、現在の天皇へと代々継承されてきました。
八尺瓊勾玉は三種の神器のうち、唯一天皇が宮中にて本物を祀りあげているとされています。
八咫鏡は伊勢神宮、草薙剣は熱田神宮と古代日本より別々に祀られています。
八尺瓊勾玉だけが天皇の元から離れずに祀られているようです。
八尺瓊勾玉ってどんな勾玉?

勾玉といえば頭部が丸く尾部が尖り、全体がアルファベットの「C」やカタカナの「コ」のように湾曲した古代の装身具です。
勾玉は縄文時代から作られていたことがわかっていて、遺跡や古墳などから多く出土しています。
当然、当時の勾玉は僕たちがイメージしているようなツルッとした綺麗な形状ではなく多少の歪さがありました。
では八尺瓊勾玉はどんな大きさでどんな形状をしているのでしょうか?
実はその実態は不明となっています。
三種の神器はどれも天皇ですら見ることが認められていない正体不明の宝物となっています。
その理由には強大な神霊が宿っているため災いが起こるなど様々な説が唱えられているが正確なことはわかっていません。
八尺瓊勾玉は出土品から察すると玉を湾曲させた形であることはおそらく間違いないと思われているが
頭に「八尺瓊」とつくことから大きな一つの勾玉や紐を通した連続した勾玉を指しているものと予想されています。
八尺(やさか): 「尺」は古代の長さの単位「咫(あた)」の転訛とされ、「八咫」は「非常に大きい」あるいは「長い」という意味合いを持つとされています。玉の周囲の長さ、尾を含めた長さ、または紐の長さなど諸説あります。
瓊(に): 「赤い玉」を意味し、瑪瑙(めのう)製であったとする説があります。
古代日本において勾玉の重要性
勾玉は日本特有のものとして縄文時代の頃から作られていたことがわかっています。
当時の勾玉の素材は動物の骨や牙などを石器などで加工して作られていました。
弥生時代になると勾玉の素材は翡翠や碧玉、瑪瑙、ガラスなどと質と技術が向上し
現代人がイメージするような勾玉へと変化していきました。
故に当時から素材の希少性や高い加工技術が必要だったため、それなりの権力や富のある人物しか身につけられませんでした。
中国の歴史書「魏志倭人伝」の記述によると、邪馬台国の女王が貢物として勾玉を二つ贈ったと記述されています。
たった二つだけでも贈り物として成立してしまうほど貴重なものということがわかります。
勾玉は装身具として身につけられることが多かったようですが
ただのアクセサリーとしてではなく、アニミズム信仰などの宗教的な要素を持っていたようです。
その形には様々な意味が込められていたようで、
陰陽マークの起源とされる太陽と月を表していたり
胎児の形を表現し、安産のお守りとしての役割があったりと考えられています。
そして、魂そのものを表しているとも考えられ様々な儀式で活用されていたとも考えられます。
八尺瓊勾玉は一度紛失した歴史がある
三種の神器である「八咫鏡」「草薙剣」「八尺瓊勾玉」は歴史上、一度海に沈んで行方がわからなくなったことがあります。
それは、平安時代末期に起こった壇ノ浦の戦いの中で発生しました。
平家側についていた当時の天皇「安徳天皇」(当時8歳)が源氏に追われ、二位の尼に抱かれ、三種の神器を抱えたまま海に身投げしたという歴史があります。
その時に三種の神器は一度消息を絶ったと言われています。
ただ、「八咫鏡」「草薙剣」は伊勢神宮と熱田神宮に本物が祀られているため
海に沈んだものはレプリカだと言われています。
しかし、八尺瓊勾玉は天皇の元から離れていないため、本物が海に沈んだことになります。
記録によると、壇ノ浦の戦い後、全国から海人さんを関門海峡に呼び集め、素潜りさせて探させたようです。
一応、無事に見つかったと言われているが個人的には疑わしさが残ります・・・笑
【まとめ】八尺瓊勾玉はどうして三種の神器として選ばれたのか?
最後に八尺瓊勾玉はどうして三種の神器となったのかを考えてみたいと思います。
八尺瓊勾玉の登場は天岩戸伝説によって日本の歴史に初めて登場しました。
天岩戸伝説は様々なことを暗示している重要な日本神話と言えるので正確なことは分かりませんが
大きな自然現象が起こった時の儀式に八尺瓊勾玉が使われていたのだと予想します。
天岩戸伝説は古代日本人が「日食」という摩訶不思議な現象をどのようにしていたのかが伺い知れる神話でもあります。
現代人からすると日食は説明できる自然現象ですが
大昔の人々は太陽が黒くなるなんて恐怖の対象でしかなかったと思います。
もしかしたら「この世の終わり」だとも考えたのかも知れません。
古代の日本人は自然の脅威は儀式によって乗り切ってきました。
八尺瓊勾玉はそんな重要な儀式にわざわざ作って臨んでいるため、
通常の勾玉とは位置付けが違うことは間違いないと考えられます。
太陽の神に使う為に作られた八尺瓊勾玉は太陽の神を頂点とした天孫族が三種の神器として代々継承していくのも納得です。
そして、八尺瓊勾玉は天皇の慈悲の象徴として今も皇居の「剣璽の間」に大切に保管されています。
という感じで八尺瓊勾玉について考えてみましたが
実際のところ真実は歴史の彼方へ消えています。
あなたもいろんな知識をお持ちだと思うので
記事の内容を参考にしつつ独自の説を考えてみて日本の歴史ロマンを一緒に感じていきましょう!!
「神社の図鑑」では他にも三種の神器についての記事を書いているので
ぜひ、読んでみてください!
何か新しい発見があるかもしれませんよ!!
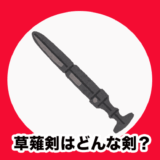 【三種の神器 – 草薙剣】古代より熱田神宮に鎮まる伝説の神剣
【三種の神器 – 草薙剣】古代より熱田神宮に鎮まる伝説の神剣  【三種の神器 – 八咫鏡】天照大御神を象徴とする伊勢神宮の御神体
【三種の神器 – 八咫鏡】天照大御神を象徴とする伊勢神宮の御神体